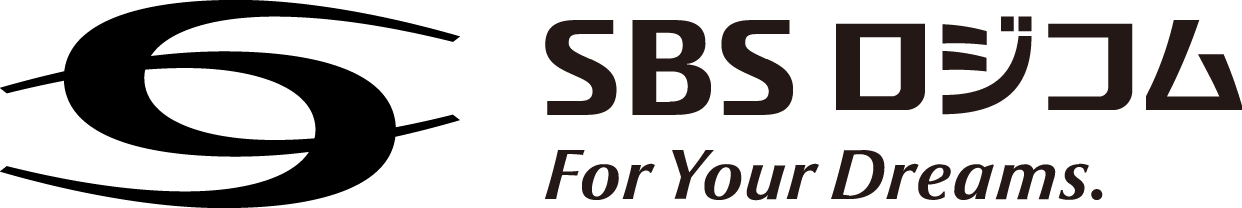最前線から見えてくる!“現代のスーパーマーケット物流”を理解するための超・基礎知識

今回の現場:SBSロジコム 佐倉物流センター支店
「人手不足」や「倉庫の機械化」、「貨物の増加」、「総合小売業界の再編」などにより、大きな過渡期を迎えているスーパーマーケット物流。現場で実務を担う運営手法やシステムなども急激に変化しています。
今回は、“現代のスーパーマーケット物流”の基礎を理解するため、前回、前々回に引き続き、SBSロジコムが運用する佐倉物流センター支店の支店長、大槻さんにお話を伺いしました。
教科書的なナレッジとは少し異なる、物流の最前線にいるからこそアップデートされた、リアルな“現代のスーパーマーケット物流”の基礎知識を見ていきましょう!
1.物流センター視点で見る、製品が消費者に届くまでの流れ

スーパーマーケット物流における製品の流れは、メーカーの製造した製品が物流センターに届き、検品や仕分けを行って各店舗に輸送し、店舗で製品を陳列して消費者に届ける、というのが基本です。メーカーから物流センターへ製品を届ける「調達物流」は、ほとんどの場合メーカー側が担っており、物流センターが行うのは、主に各店舗への輸送になります。
メーカーと店舗の間に物流センターがある形態は、1960年代、高度経済成長期に製造業で大量生産の体制が構築された時代から、徐々に広まっていったといわれています。
「製品が消費者に届くまでの過程を川だとすると、上流にあるのがメーカーで下流がスーパーマーケット、中間にあるのが物流センターですね。この流れは現在でも大きくは変わっていません。すごく古い時代は、メーカーが商品をつくり、直接小売店に納品していたようです。ただ、メーカーが増え、製品も増えると、小売店の納品口が大渋滞になってしまいますし、メーカーにとっても、遠方の小売店まで納品するのは大きな負担になります。そこで、製品の流れを集約して管理する場所として、物流センターが生まれました」
現在でも、ごく少数の店舗であればメーカーが直接納品することもあるようですが、ある程度の規模感のスーパーマーケットには、ほぼ間違いなく物流センターがあるそうです。
2.現在の物流センター運営の主流である“3PL契約”とは

古くから物流センターとよく似た機能を担ってきたのが食品問屋です。メーカーから製品を仕入れ、スーパーマーケットなどへの販売を行なう食品問屋は、商品の保管や物流管理などの役割も担っています。
かなり古い時代には、食品問屋を通す製品がほとんどでしたが、徐々にスーパーマーケット自身で物流センターを建設することも増えていきました。ですから、現在の物流センターは、スーパーマーケットが所有するものと、食品問屋が所有するものに分かれているそうです。
佐倉物流センター支店の場合、所有しているのはスーパーマーケットチェーンのカスミ。SBSロジコムは、カスミと「3PL契約」を結び、物流管理や配送業務を担っています。
「近年、スーパーマーケットの物流センター運営の主流になっているのが、スーパーマーケット側が物流センターを建設し、物流会社が配送業務や入庫業務などを請け負う『3PL(3rd Party Logistics)契約』という手法です。これは、言ってみれば、“物流に関する業務を専門家に任せる”契約で、スーパーマーケット側にとっては物流会社の運送網を活用できたり、物流の課題を専門的なノウハウで対応できたりするメリットがあります。近年、商品や店舗数の増加などにより物流が高度化しているなかで、『3PL契約』によって手間のかかる物流を外部に委託することで、お店は店舗運営に専念できるのです」
3.貨物管理の要となるシステムが、“WMS”と“WES”

現在、ほぼすべての物流センターで貨物の管理を担っている重要なシステムが、「WMS(Warehouse Management System)」と「WES(Warehouse Execution System)」です。
「WMS」は、物流センターで貨物を入荷してから出庫するまでの在庫管理や流通加工、帳票類の発行、棚卸などを一元的に管理するシステムです。入出庫作業の高速化・正確化、ヒューマンエラーの削減、人員配置の最適化ができるというメリットがあります。
一方で、物流センターの作業を効率化するシステムである「WES」は、倉庫内のさまざまなデータを蓄積し、作業指示や進歩管理、優先順位づけ、担当者の割り当てなどの意思決定をサポートします。機械化の進んだ物流センターでは、マテハン機器の制御や管理に特化した「WES」もあるそうです。
※マテハン機器…物流や製造の現場で、貨物などの移動や運搬を効率化する機械の総称
「貨物の管理という面では、スーパーマーケットの製品と、例えば家具などを管理するのは手法が大きく異なりますし、物流センターの“機械化の進度”などによっても最適な手法は異なるため、『WMS』にもさまざまな種類があり、基本的には物流センターや作業内容に合わせて構築するシステムですね。ちなみに、佐倉物流センター支店ではカスミ様の『WMS』を使っていますし、SBSロジコムのほかの倉庫などでは、別の『WMS』で運用しています」
4.物流の最重要課題である人手不足と機械化にどう対応する?
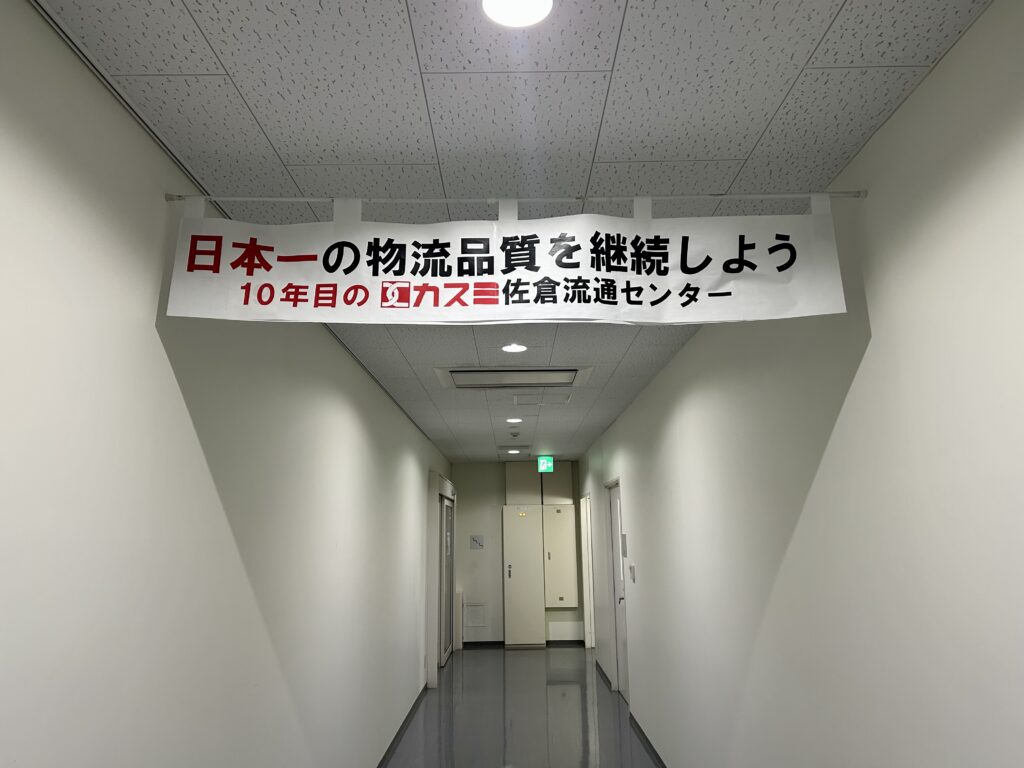
前回、前々回の記事でも紹介したように物流業界全体で最重要な課題が、ドライバーなどの人手不足です。
現在では、課題に対応するため、なんと本来競合であるはずの同業他社と手を組み、1台のトラックで、異なる系列のお店に貨物を届けたり、例えば食品と雑貨など、種類の異なる貨物を積んだりすることも珍しくありません。
「ドライバー不足は本当に深刻で、多くの物流会社が自社だけでは手が回らず、1台のトラックを複数の物流会社でシェアすることが増えましたね。ただし、逆に言うと、人が足りないからこそドライバーを希望する人にとってはチャンスで、多くの物流会社さんがドライバーさんをとても大事に育成していると思います。我々の佐倉物流センター支店は、運転技術の面で配送が難しい店舗が少ないので、運転が好きであれば誰でも働きやすい職場です。5名以上女性ドライバーさんが在籍していた時期もあるので、今後は、隙間時間などを活用したい女性の活躍を期待しています」
物流センター内の業務においても、人手不足により機械に頼らざるを得ない部分が多くなり、物流センターにも機械化の波が押し寄せています。
とはいえ、物流業界ではおよそ10年経つと新しい機能を持った機器が登場することが多く、また、配送する店舗や製品の数などによっては人力で行ったほうが費用対効果の高いこともあり、現状では、よほどの資金力のある企業でないと思い切った機械化は難しいようです。
「総合小売業界で再編が進むなど先行きが不透明な状況で、大規模な機械化は難しいと考える物流会社が多いですね。現実的には、汎用性のある自動仕分け機などによって、『これまで10人必要だったところを5人にする』くらいの機械化が一般的かなと思います。今後、例えばの話ですが、カスミ様がどこかほかのグループと提携し、『物流はSBSロジコムではなく、そちらに任せる』ということになるかもしれないため、我々としては常に危機感があります。『SBSロジコムさんでないと安心して任せられない』と思っていただけるように、物流の品質を少しでも高めていくことが現在の物流では求められています。佐倉物流センター内に飾ってあるように、SBSロジコム全体で、“日本一の物流品質”を目指していきたいですね」